外来種問題は生物多様性を脅かす重大な問題の一つとされています。
また、昨今は『池の水を抜く』シリーズのテレビ番組や、”生き物系”や”ガサガサ系”と呼ばれるYouTuberが駆除活動を発信することで、より身近な環境問題だと感じる人も多いかもしれません。
そんな外来種駆除のために、サメを使おうという取り組みがあったのをご存知でしょうか?
実際に大西洋の広範囲で猛威を奮っている外来種、ハナミノカサゴを駆除するために、野生のサメを訓練した人たちがいました。
- 大西洋でハナミノカサゴはどんな問題を起こしているのか?
- サメを使った対策の結果はどうなったのか?
今回は、外来ミノカサゴ問題とサメを使った対策について解説をしていきます!
解説動画:危険生物バトル?サメを調教して外来種ミノカサゴを駆除しようとした末路とは?
このブログの内容は以下の動画でも解説しています!
※動画公開日は2025年3月24日です。
外来種は海にもいる
外来種について「海外から日本に来ている危険な生物」や「山や川で問題になっている生き物」というイメージを持っている人も多いと思います。
そこでまずは、外来種の定義や海の外来種問題について簡単に説明します。
外来種は人間活動により移入された生物
外来種の定義は「時期や意図的かどうかに関わらず、人間活動によって本来の生息域ではない場所に移入された生物」です。
そのため、海外から日本に来た生物だけでなく、以下のような生き物も全て外来種となります。
- 日本から海外に移入された生物
- 日本国内のA県からB県へ移動された生物
- 品種改良などで作られた、そもそも”本来の生息域”が存在しない生物
なお、「人為的に移入された」という定義上、自ら生息域を広げた人間そのものは外来種に含まないのが一般的な考えです(外国人旅行者や移民の方々を外来種扱いする差別主義者がいますが、色々な意味で恥ずかしいのでやめましょう)。
また、外来種に関して「外来種=悪者」と誤解している人をよく見かけますが、外来種の中には新しい環境に馴染めずに死んでしまうものや、野菜や家畜など我々の生活に欠かせない生き物も多くいます。
しかし、人間社会や生態系に重大な悪影響をもたらす外来種もいます。そうした生物は侵略的外来種と呼ばれます。
こうした侵略的外来種は、移入先に元々いた生物を捕食したり、資源を奪い合ったり、病気を媒介したり、あるいは交雑するなど、様々な形で在来生物に悪影響を与えます。
また、農作物を食い荒らす、人間に噛みつくなど、移入先地域に経済的・人的被害をもたらすこともあります。
海の外来種問題
人間活動によってある海域から別の海域に運ばれる生き物も外来種なので、海にも外来種問題が存在します。
例えば、タンカーなどの大型船は船のバランスを保つために搬入・排水を行うバラスト水によって、ワカメやムール貝などの様々な生き物が本来の生息域以外の場所に拡散して問題を起こしています。
また、タマカイとクエを交雑させた養殖魚、通称”タマクエ”(クエタマとも言う)が自然の海で漁獲され、養殖場から逃げ出した可能性が指摘されています。これも外来種に当たります。
外来種の定義や駆除の是非については、以下の記事でも解説しているので、詳しくはこちらをご参照ください。

外来種としてのハナミノカサゴ
侵略的外来種のうち、海水魚の中で最も悪名高いのがミノカサゴ類、主にはハナミノカサゴです。
本記事では便宜上「ハナミノカサゴ」とだけ表記しますが、大西洋域にはハナミノカサゴの他にも近縁種が定着しているとされています。基本的には「大西洋域を侵略しているミノカサゴ類」の話をしていると思ってください。
美しいが毒を持つ魚
ハナミノカサゴはスズキ目フサカサゴ科ミノカサゴ属に分類される魚で、日本近海を含むインド・太平洋の沿岸域に分布しています。
近縁種で見た目の似た魚としてミノカサゴもいますが、ハナミノカサゴは顎下にも縞模様がある、背鰭・臀鰭・尾鰭に小さな黒い斑点が目立つなどの特徴で見分けることができます。


長いヒレと縞模様が美しい魚ですが、鰭にある棘に強い毒を持っています。
刺されると患部が大きく腫れあがり、激しい痛みや呼吸困難などの症状を引き起こすため、危険生物として紹介されることも多い魚です。
大西洋域で爆発的に拡大
そんなハナミノカサゴは北米・中米・南米大陸の大西洋側沿岸において、非常に厄介な侵略的外来種として大問題になっています。
最初に大西洋で確認されたのは、1980年代の米国フロリダ州の沿岸だとされています。
侵入経路についての有力な説は、飼育していた人間による放流です。
ハナミノカサゴは、模様が美しく泳ぐ姿も優雅で、アクアリストには人気の魚ですが、先述の通り鰭には毒針を持ち、成長すれば30~40cm前後にはなるので、飼いきれなくなった人間や業者が海に捨てたと思われます。
この流入経路について、「ハリケーン・アンドリューによって水族館が破壊され、そこから逃げ出したハナミノカサゴが原因だ」とする説がよく紹介されていますが、アンドリューが発生したのは、最初にフロリダでハナミノカサゴが発見された後の1992年であり、流出した個体数も6尾程度だったとされています。
したがって、ハリケーン被害を受けた水族館以外にも、ハナミノカサゴ流出の経路があったことは間違いないでしょう。
大西洋の海に放たれたハナミノカサゴは、その後爆発的な勢いで個体数を増やし、生息域を拡大していきました。
2000年頃にはフロリダ州より北側のノースカロライナ州近海まで広がり、翌年には記録が一気に増加。数年のうちにニュージャージー州近海まで北上するのと同時にバハマに南下、2007年にはカリブ海まで拡大し、2009年には南米まで到達。現在はブラジルでも確認されており、凄まじい勢いで生息範囲を広げています。
拡大した各海域における生息密度も凄まじいことになっており、原産地のインド・太平洋に比べ、10倍近い密度で確認された場所もあるほどです。
たった20~30年の間に、ハナミノカサゴは大西洋の広範囲に定着してしまいました。
実際に大西洋で撮影されたハナミノカサゴの映像↓
外来種ハナミノカサゴが引き起こす問題
外来種ハナミノカサゴの何が問題で、何故ここまで生息域が拡大したのでしょうか?
捕食被害
ハナミノカサゴが外来種として生態系にもたらす主な被害は捕食です。
彼らはエサに関する選り好みをせず魚類や甲殻類などを幅広く捕食するため、沢山の在来種を食べてしまいます。
これによって在来種の数が減ってしまうこと自体も問題ですし、元々そうした生き物を食べていたハタ類などの大型魚も、エサを奪われることで悪影響を受けてしまいます。
2012年に発表された論文によれば、バハマのサンゴ礁で外来ミノカサゴ類の影響を調べたところ、たった2年間で調査海域における捕食者の40%をミノカサゴ類が占めるようになり、在来魚42種の個体数が平均65%減少したという結果が得られています。
また、ハナミノカサゴの捕食によって草食魚の数が減少することで藻が過剰に増殖し、サンゴを覆ってしまって光合成を妨げるなどの問題も引き起こします。
食べられにくく増えやすい
ハナミノカサゴの厄介な点として、他の捕食者に食べられにくい上に数を増やしやすいという点が挙げられます。
ハナミノカサゴは先述の通り毒針を持っている比較的大きな魚なので、天敵がほとんど存在しません(サンゴ礁において、最大30~40cmは割と大きなサイズです)。
加えてハナミノカサゴは卵を産む数も多く、1尾のメスは1回の産卵で2,000~15,000個もの卵を産み、それを数日ごとに繰り返します。
この卵はゼラチン質に包まれた状態で海流に流され、さらに生息域を拡大させていきます。
実際にブラジルで発見されたハナミノカサゴのDNAを調べた研究によれば、新たに放流された個体ではなく、カリブ海に定着した個体群に由来している可能性が高いそうです。
このように、増加および拡散しやすい特徴を持つハナミノカサゴは、先程触れた通り新天地で爆発的に勢いをつけ、もはや完全な駆除は不可能であると言われています。
なぜ日本近海では問題にならないのか?
ここまで外来種として問題になっているハナミノカサゴが、なぜ日本を含む原産地では問題になっていないのでしょうか?
正直はっきりとした理由は不明ですがX(旧Twitter)で意見を募集したところ、「捕食者に食べられているのでは?」や「美味しいから食べられているのかも?」などの意見が寄せられました。
また、ハナミノカサゴの被害を受けているバハマ、サン・サルバドル島で行われた研究では、波や海流の影響を受けにくい場所では、影響を大きく受ける場所に比べてハナミノカサゴの密度や個体数が20~120倍も大きいという結果が得られています。
日本国内で爆発的に増加していない原因は不明ですが、捕食者以外にも、こうした非生物的要因が関係しているのかもしれません。
ハナミノカサゴ駆除のためにサメを訓練した結果
ハナミノカサゴによる悪影響を少しでも抑えようと、様々な駆除活動が実施されています。
その中でも一時期注目を集めたのが、サメを使った駆除です。
捕獲したハナミノカサゴをサメに餌付け
善意で集まった一部のダイバーが、現地に生息するサメ(厳密に言えばハタ類やウツボ類も含む大型捕食者)にハナミノカサゴを食べてもらえるよう訓練を始めました。
訓練方法としては以下の通りです。
- スピアフィッシングによりハナミノカサゴを捕獲する。
- 突き刺した状態のハナミノカサゴをサメたちに餌付けする。
- これを繰り返し、ハナミノカサゴを襲う習性を身につけさせる。
訓練の対象となる魚種は明確に決まっていなかったようですが、ペレスメジロザメやコモリザメ、オオメジロザメ、グリーンモレイなどが餌付けされていたようです。
実際にハナミノカサゴを餌付けしている様子はコチラ↓
毒針に影響されることなく食べるサメたち
水中銃の先に突き刺さったハナミノカサゴをサメたちに食べさせることには成功しています。
「ハナミノカサゴの毒はサメに効かないの?」と気になる人もいると思いますが、サメが毒で苦しむことは無かったようです。
詳細は不明ですが、ヒラシュモクザメなどのサメはアカエイ類の毒針が刺さっても平然とエイを食べているので、サメ類には魚の毒に対し何かしらの耐性があるのかもしれません。
また、サメたちにハナミノカサゴを与えると頭から食べるため、毒針が喉に引っかかることもなかったようです。
問題が解決するどころかサメ被害が発生
この訓練の最終目標はサメたちが自発的にハナミノカサゴを狩ることでしたが、そこまでの成果は得られず、むしろ別の問題を引き起こしました。
ダイバーからエサが手に入ると学習したサメたちは、執拗にダイバーたちを追い回したり、駆除した魚を入れておくための容器から直接ハナミノカサゴを奪おうとすることさえありました。
挙句の果てに、ハナミノカサゴの駆除活動中にダイバーが実際にサメに噛まれてしまったり、駆除活動中にサメやウツボを追い払う人員が必要になったりと、駆除活動そのものへの悪影響も出てしまいました。
こうした事実を踏まえ、複数の研究者がまとめた西大西洋におけるハナミノカサゴ対策についての報告では、外来ミノカサゴを襲うように在来の捕食者を訓練する方法は「Unsuccessful(失敗した)」と評価され、「駆除したミノカサゴ類は密閉して持ち帰るべきだ」という助言が盛り込まれています。
同報告書内では有効な対策として、
- スピアフィッシングによる組織的な駆除活動の実施
- 駆除数に応じた賞金を出すトーナメントイベントの開催
- 食品や加工品としての利用を促し漁業者の捕獲を促進
などの対策が推奨されていました。
ハナミノカサゴを根絶することは恐らく不可能ですが、「根絶が無理だから何もしない」という0か100かの極端な思考ではなく、少しでも生態系に対する悪影響を減らすためにやれることを継続することが大事なのだと思います。
あとがきに代えて注意喚起
今回は大西洋におけるハナミノカサゴ問題と、サメを使った対策の失敗について解説をしてきました。
最後にまとめの代わりとして2つの注意喚起をしておきます。
ペットの放流は絶対ダメ
自分が飼っている魚は、外国産か日本産かに関わらず海や川に捨てないでください。
水温や環境が合わないなどの理由で死滅する可能性もある一方、今回のハナミノカサゴのように、取り返しのつかない大惨事になるリスクもあります。
飼育由来の海水魚が日本で大事になったケースは現状ないはずですが、淡水域においては「飼えなくなった」や「野外で釣りたいから」などの身勝手な理由で侵略的外来種が繰り返され、深刻な問題になっています。
外来種の放流は絶対にやめて下さい。
野生動物に安易な餌付けをするべきではない
基本的に野生動物への餌付けはロクな結果になりません(詳しくはコチラも参照)。
今回のように人間が襲われたり、逆に野生動物を傷つけてしまうなど、様々な問題を引き起こします。
現状エコツーリズムの一環としてサメへの餌付けが行われている地域もあり、それが保護に役立っているという見方もありますが、やはり反対する人も多いです。
仮になんらかの事情で続けるとしても、やり方を制限したり、影響について調査をすべきでしょう。少なくとも、一般人が安易にやるべき理由はありません。
野生動物はあくまで野生動物です。時に恩恵をもたらすことはあっても、あなたの友達ではないし、思い通りになる存在ではありません。このことは肝に銘じておくべきです。
参考文献
- Animal Diversity Web『Pterois volitans Red firefish』(2025年3月25日閲覧)
- Aylin Ulman, Aylin Ulman, Fadilah Z. Ali, Fadilah Z. Ali et al.『Lessons From the Western Atlantic Lionfish Invasion to Inform Management in the Mediterranean』2022年(2025年3月25日閲覧)
- The Dodo(Ben Guarino)『Feeding Lionfish To Wild Sharks Is A Bad Idea With Good Intentions』2014年(2025年3月25日閲覧)
- NOAA Fisheries『Impacts of Invasive Lionfish』(2025年3月25日閲覧)
- Science(Virginia Morell)『Mystery of the Lionfish: Don’t Blame Hurricane Andrew』2010年(2025年3月25日閲覧)
- Scuba Diving(Alexandra Owens)『Why You Shouldn’t Feed Lionfish to Sharks』2024年(2025年3月25日閲覧)
- University of Miami(Laurel Zaima)『The Consequences of the Indo-Pacific Lionfish invasion into Atlantic Waters』2015年(2025年3月25日閲覧)
- ナショナルジオグラフィック日本版『侵略的外来種のミノカサゴ、ついにブラジル沿岸にも定着』2022年(2025年3月25日閲覧)
- 南日本新聞『いないはずの人工交雑魚「クエタマ」が鹿児島湾で相次ぎ目撃 養殖場から逃げた? 生態系への影響危惧』2023年(2025年3月25日閲覧)
初心者向け↓
中級者向け↓

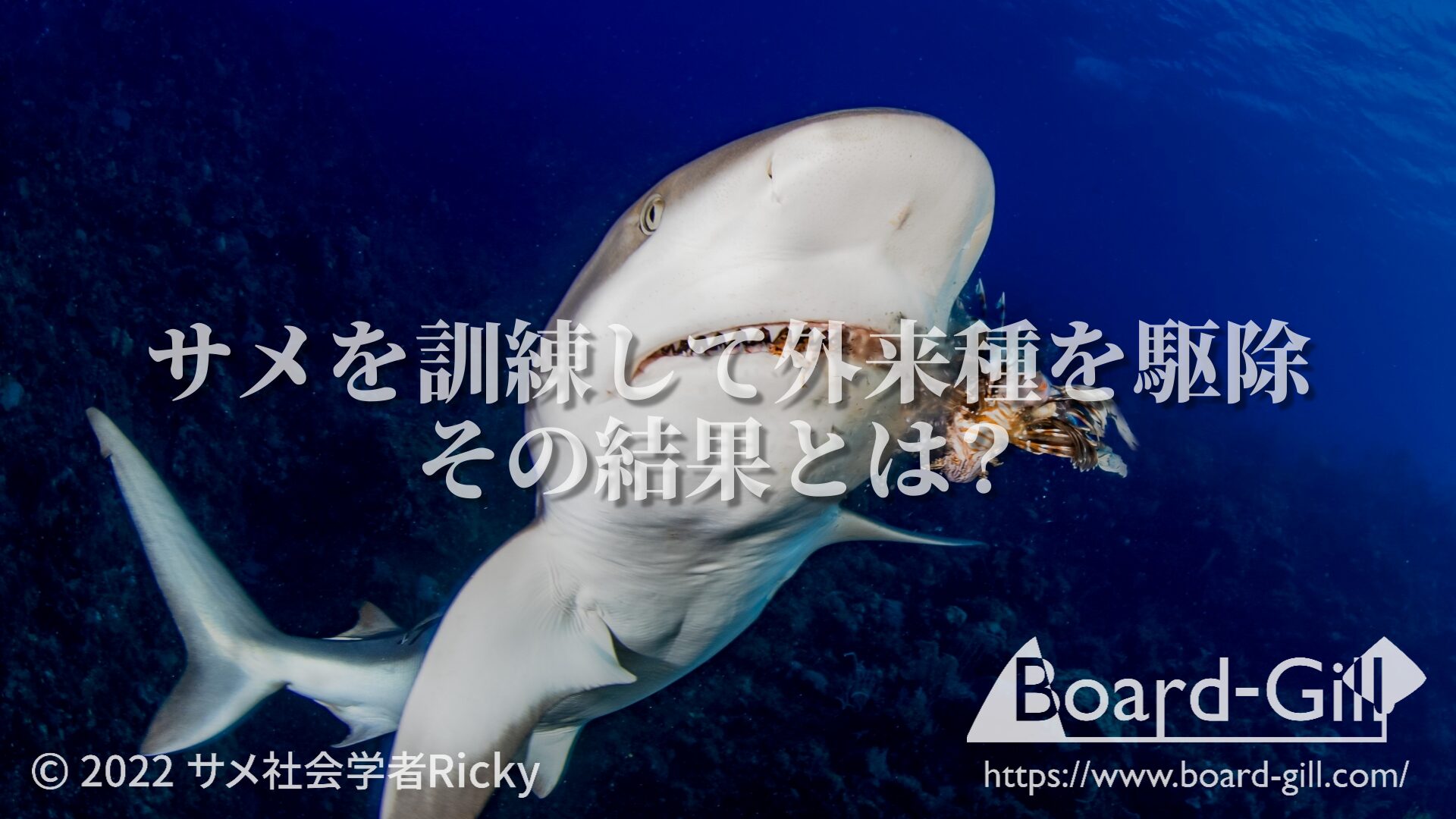
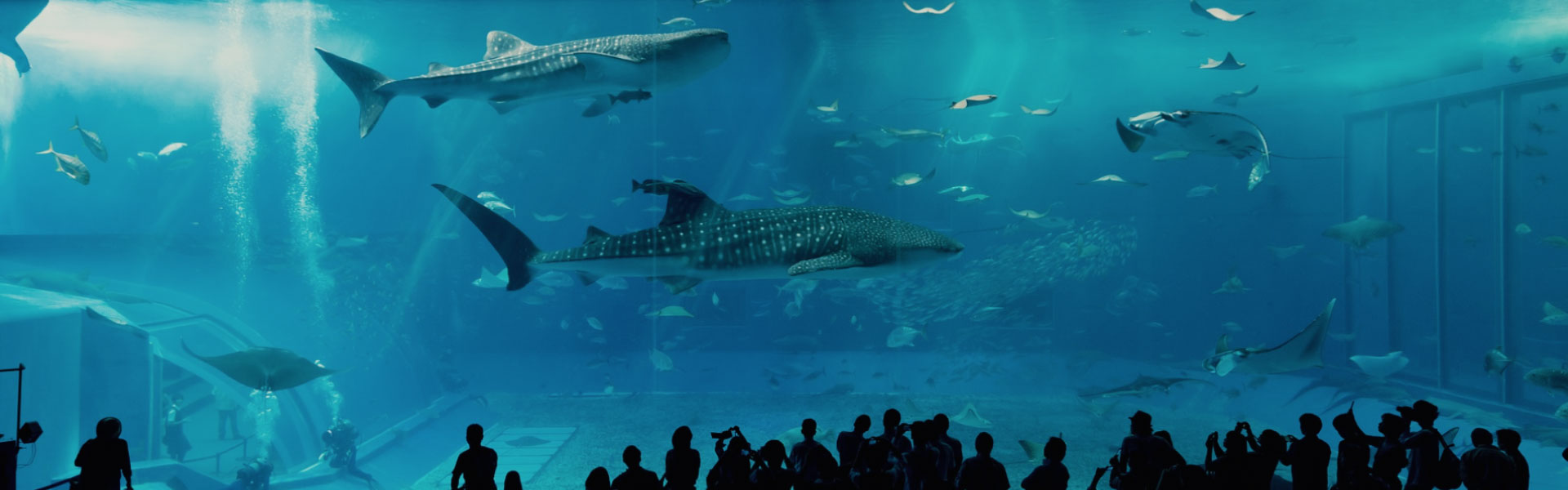
コメント